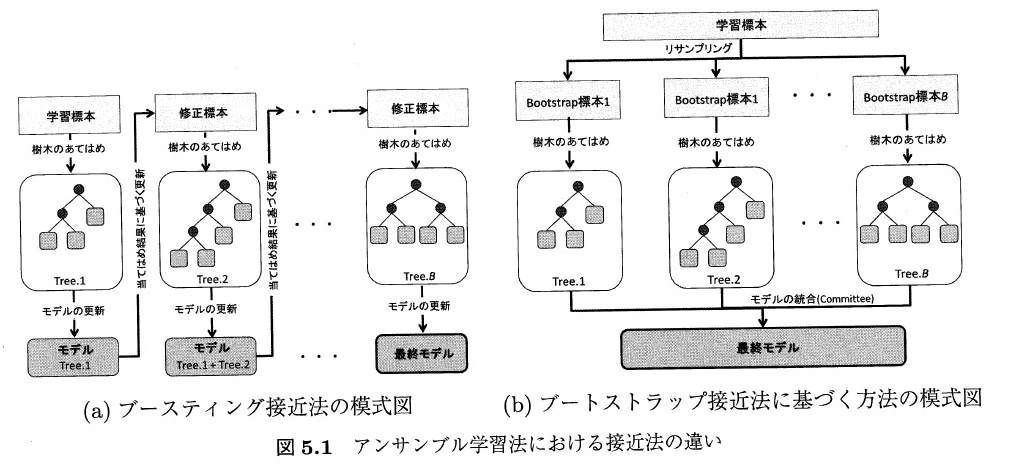決定木法メモ¶
「樹木構造接近法」(下川敏雄ら、共立出版)による
CART(Classification and Regression Trees)法¶
データ集合を$\mathcal{L} = \{y_n, \boldsymbol{x}_{n}\}$ $(n=1,\cdots,N)$とする。
木(tree)の成長過程¶
最初は一つのノード(root)にすべてのデータがあるとして、それらをポリシーにより枝分かれさせていく。
あるノード(節)を子ノードに分けるポリシーは、ノード内の不均一性測度を小さくすることである。 あるノード$t$の回帰残差を $$ r_{reg}(t) = \frac{1}{N(t)}\sum_{n\in t} \{y_n - \bar{y}(t)\},\quad \bar{y}(t)=\frac{1}{N(t)}\sum_{n\in t} y_n $$ を用いて、不均一性測度は、 $$ R(t) = pr(t)r_{reg}(t), \quad pr(t) = N(t)/N $$ で定義する。
以上は回帰木の場合である。
分類木の場合¶
応答$y_n$は$K$個のクラスのいずれかの値をとる「分類木」について考える。
ノード$t$において応答(値)が$k$をとる確率は $$ pr(k|t) = \sum_{n\in t} \mathbb{1} (y_n = k)/ N(t) $$ である。ここで$\mathbb{1}(\cdot)$はカッコ内が真なら1, 偽なら0を撮る関数である。$t$における予測値は、その木にもっとも多い応答の数として次のように定義する(多数決)。 $$ \newcommand{\argmax}{\mathop{\rm arg~max}\limits} \hat{k}(t) = \argmax_{k} pr(k|t) $$
この場合は、ノード$t$の不均一性測度として次のものが考えられる
- 誤分類率(期待値に一致しない確率): $r_{c1}(t) = 1 - pr(\hat{k}(t)| t)$
- Gini係数: $r_{c2}(t) = \sum_{k\neq k'} pr(k|t) pr(k'|t) = \sum_{1\le k \le k'} pr(k|t) (1- pr(k|t))$
- エントロピー基準: $r_{c3} = -\sum_{1\le k\le K} pr(k|t)\log pr(k|t)$
$t$を$t_L$と$t_R$に分岐させる規則を式で表すと $$ s_t^* = \argmax_{s_t\in S_t} \Delta R(s_t, t),\quad \Delta R(s_t,t) = R(t) -R_L (t_L) - R_R(t_R) $$ と表される。要は、不均一性測度が最大になるように分類するということである。
木の刈り込み過程¶
木を成長させていけば、$R$は減少していく。最後は1つのノードに一つのデータだけになることになってしまう。それはやりすぎである。そこで木が大きくなりすぎないように複雑度のペナルティを加え、それが最小にすることを考える。
木のノード集合$T$のうち、末端のノード(葉)の集合を$\tilde{T}$とし、その個数を$|\tilde{T}|$で表す。複雑性コストを加えた量 $$ R_{\alpha}(T) = R(T) + \alpha |\tilde{T}| $$ を最小にする木をみつける。
最適な木の決定¶
この説の記述は省略が多く、わかりにくいが、全体としては、データの一部分を学習データ、残りをテストデータとして、交差検定を行って最適な木をみつけるポリシーが書かれていると思う。
CARTの利用例¶
住宅価格データBoston使う。(パッケージ MASSに含まれている。)
持ち家価格の中央値(medv)をその他の量を説明変数として、影響を与える要因を分析する。
- CART法は、パッケージrpartに入っている
- "medv ~ ."はmedvが目的変数、それ以外を説明変数とするという意味
- 目的変数(応答)が連続的な値の場合は回帰木(anova)を、因子型であれば分類木(class)を利用。
data(Boston, package = "MASS")
names(Boston)
library(rpart)
rtree0<-rpart(medv~., data=Boston, method="anova", control=rpart.control(cp=0))
plot(rtree0, uniform=TRUE, margin=0.1)
text(rtree0, cex=0.6)
アンサンブル学習法¶
アンサンブル学習法は、開会学習あるいはデータ・マイニングの分野では、集団学習(Committee Machine)と呼ばれている。
方法はおもに2つに分類される。
- ブースティング接近法 モデルへの木の追加過程において、予測誤差を逐次改善する方法
- ブートストラップ接近法 ブートストラップ標本に対して、あてはめた個々の基本学習機の平均値(回帰問題の場合)、あるいは多数決(分類問題)よりモデルが得られる。
「樹木構造接近法」図5.1